子どもは着物や袴などのきれいな衣装を着て、神社に行きます。
神社ではお祈りをして、「これからも健康でいられますように」と願います。
写真を撮ったり、おいしいお菓子やごちそうを食べたりもして、お祝いします。
今ではレンタル衣装や写真館も多く、子どもに負担を少なく楽しくお祝いできる方法も増えています。
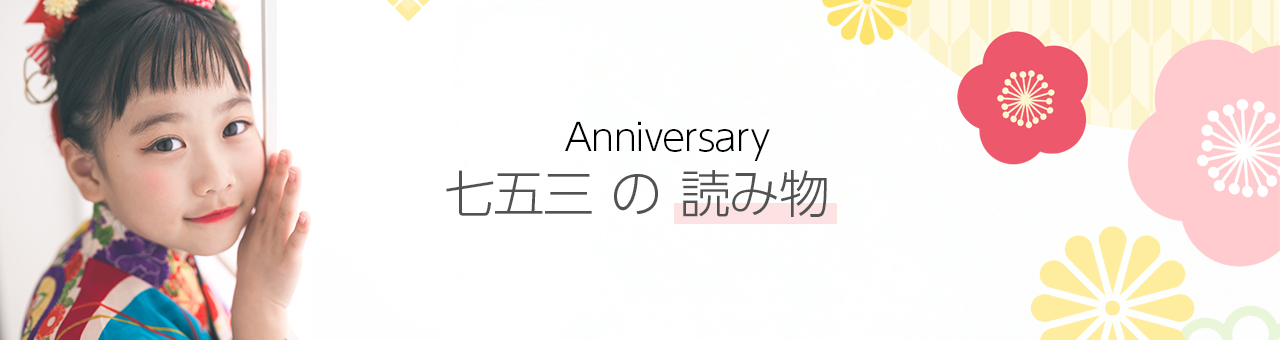
伝統的な文化であると共に、お子様の成長の過程を写真を残す絶好の機会、七五三。
知っていなければいけない、知るべき情報をまとめさせて頂きました。


千葉県千葉市花見川区花園1-9-3 101にある子供写真スタジオSTUTIO LEMON 101!
オシャレに美しい七五三写真を撮影できます!
JR総武線 新検見川駅徒歩1分
七五三撮影はこちらから!
七五三前撮り・後撮りもやっています!
七五三は、日本の子どもにとって大切な行事です。子どもの成長を祝って、神社に参拝し、健康や幸せを祈るお祝いです。これは、3歳、5歳、7歳のときに行います。子どもたちは特別な着物や袴を着て、家族みんなで神社へお参りします。
子どもが無事に大きくなったことを神様に感謝し、これからも元気に育つよう願うためです。特に、3歳と5歳の男の子、7歳の女の子は、昔から特に大切な年と考えられてきました。

子どもは着物や袴などのきれいな衣装を着て、神社に行きます。
神社ではお祈りをして、「これからも健康でいられますように」と願います。
写真を撮ったり、おいしいお菓子やごちそうを食べたりもして、お祝いします。
今ではレンタル衣装や写真館も多く、子どもに負担を少なく楽しくお祝いできる方法も増えています。
一般的には、「11月の第2の土曜日や日曜日」にお祝いします。ただし、家族の都合や子どもの体調に合わせて、早めや遅めに行うこともあります。
近年では七五三撮影と七五三の参拝を分ける七五三前撮り・七五三後撮りなども主流となってきております。
七五三は、「子どもの成長に感謝し、これからも元気に育つよう願うお祝い」です。家族や地域の人たちと一緒に、楽しく撮影やお祈りをして、素敵な思い出を作る大切な行事です。
お子様の健やかな成長を祝う七五三は、ご家族にとって大切な一日です。
しかし、慣れない着付けや移動、待ち時間などで、お子様が疲れてしまわないか心配という方も多いのではないでしょうか。
ここでは、当日の流れをイメージしやすい一日のスケジュール例をご紹介します。
また、準備や注意点も併せて解説しますので、ご参考ください。
【お祝いの流れのポイント】
・ゆとりを持ったスケジュールを組む
・事前準備をしっかり行う
・お子様の気分や体調に合わせて調整する
これらを意識すれば、家族みんなが笑顔の最高の一日になるでしょう。
これはあくまで例です。
お子様の性格や体調、写真の撮影などによって柔軟に調整してください。
特に祈祷の時間は混雑状況により変動しますので、余裕を持った計画が大切です。
7:00~8:00頃:起床・朝食
いつもより少し早めに起きて、ゆったりと朝食をとりましょう。
お子様の機嫌が良い時間帯を意識し、早めに行動を開始するのがポイントです。
8:00~10:00頃:着付け・ヘアメイク
ご自宅や美容室、スタジオで着付けとヘアメイクを行います。
特に女の子は準備に時間がかかることも多いので、余裕を持ってスケジュールを組みましょう。
早朝の予約は混みやすいので事前予約をおすすめします。
10:00~12:00頃:写真撮影(前撮り・当日撮影)
スタジオや神社での写真撮影の時間です。
お子様が疲れないよう、休憩をはさみつつ進めてください。
当日に神社で祈祷前後に撮影を行う場合もこの時間に合わせましょう。
12:00~13:00頃:神社・仏閣へ移動・軽食
撮影後は目的地の神社やお寺へ移動します。
移動中や到着後に空腹にならないよう、食べやすい軽食を持参しましょう。
13:00~14:00頃:受付・ご祈祷
到着後、手水舎で清めて祈祷の受付を行います。
混雑状況によって待ち時間もありますので、お子さまの気持ちを和らげるおもちゃや絵本も準備しておくと良いでしょう。
祈祷時間は15分~30分程度ですが、待ち時間を含めて1時間以上かかることもあります。
14:00~15:00頃:境内にて記念撮影・千歳飴授与
祈祷が終わったら、境内や周辺で記念写真を撮ります。
千歳飴や記念品を持って、笑顔の家族写真を残しましょう。
お子さまの体調や気分に合わせて無理なく進めてください。
15:00~16:00頃:着替え・帰宅・移動
疲れたら着物を脱いでリラックスさせてあげてください。
レンタル衣装の返却や、次の予定のために移動します。
16:00~以降:お祝い会食や家族の時間
家族や親戚と集まり、食事やお茶会を楽しみます。
子供の好きなメニューやケーキで、お祝いムードを高めましょう。
・
・事前に予約や準備を早めに済ませておきましょう。
・持ち物リストを作って、忘れ物のないようにしましょう。
・お子さまに当日の流れを説明しておくと協力してくれます。
・疲れたときは無理せず休憩を挟みましょう。
七五三はご家族にとって大切で心温まる行事です。
計画的に進めれば、きっと最高の思い出になります。
楽しい一日をお過ごしください!

七五三のお祝いは、子どもの健やかな成長を願う大切な行事です。お参りの日をどう決めるか迷うこともありますよね。実は、七五三の本祭は「11月15日」と決まっていますが、その日にちにこだわる必要はありません。ここでは、理想的なお参りの日の選び方についてご紹介します。
正式には「11月15日」が七五三の本祭日です。この日を選ぶ理由は、平安時代からの伝統により、旧暦の11月15日が子どもの成長祈願の日とされてきたからです。晴れ着や衣装を整えて、多くの家族がこの日に参拝してきました。
現代では、11月15日にこだわらなくても大丈夫です。子どもや家族の都合に合わせて、土日や祝日、連休の中で都合の良い日を選ぶのが一般的です。できるだけ混雑の少ない日や、家族みんなが揃いやすい日を選びましょう。
結局のところ、七五三のお参りの日は、「子どもと家族が一番都合の良い日」を選ぶのがベストです。11月15日を避けて、平日や天気の良い日を選ぶことで、ゆったりと祝うことができます。大切なのは、みんなが笑顔でお祝いできる日を見つけることです。安心してお参りできる日を選んで、素敵な七五三の思い出を作りましょう!
お子様の健やかな成長を祝う七五三。
着物を着せてお祝いしたいけれど、レンタルと購入、どちらが良いのか迷っているご家庭も多いのではないでしょうか。
それぞれにメリットとデメリットがあり、ご家族の状況や七五三への考え方によって最適な選択は変わってきます。
ここでは、七五三の着物の「レンタル」と「購入」それぞれの特徴を詳しく比較し、あなたに合った選び方のヒントをご紹介します。
まずは、手軽さが魅力のレンタルから見ていきましょう。
レンタルのメリット
1. 初期費用を抑えられる:
購入に比べて、一度にかかる費用を大幅に抑えることができます。
七五三の準備全体にかかる費用を考えると、大きなメリットです。
2. 保管や手入れの手間がない:
着物の保管場所や、着用後のお手入れ(クリーニングなど)を心配する必要がありません。
着用したら返却するだけなので、とても手軽です。
3. トレンドや好みに合わせて選べる:
毎年違うデザインや色の着物を選べるため、その時々のお子様に似合う最新のトレンドや、ご家族の好みに合わせた着物を選ぶことができます。
4. 必要なものが一式揃う:
多くのレンタルプランでは、着物本体だけでなく、帯や小物、草履、バッグなど、必要なものが一式セットになっているため、自分で一つ一つ準備する手間が省けます。
レンタルのデメリット
1. 繰り返しの利用は割高になることも:
お子様が3歳と7歳(または5歳)で七五三を迎える場合、その都度レンタルすると、合計金額が購入費用に近づくこともあります。
兄弟姉妹で着回しを考えている場合は、さらに割高になる可能性があります。
2. サイズやデザインの選択肢が限られる場合がある:
特に人気の着物や、特殊なサイズの場合、直前だと希望のものが借りられないことがあります。
予約は早めに行う必要があります。
3. 汚損・破損時の弁償リスク:
着物を汚したり破損させたりした場合、別途クリーニング代や修理代、あるいは弁償費用が発生する可能性があります。
お子様は元気なので、注意が必要です。
4. 着用日や返却日の制約:
レンタル期間が決まっているため、着用日や返却日を守る必要があります。
急な体調不良などで延期になった場合の対応も確認が必要です。
次に、記念として残せる購入のメリット・デメリットを見ていきましょう。
購入のメリット
1. 完全に自由な選択とサイズ調整:
お子様の体格に合わせて、ぴったりとサイズ調整された着物を選ぶことができます。
色柄も豊富で、誰とも被らないオリジナルの着物を見つけられます。
2. いつでも何度でも着用可能:
七五三当日だけでなく、お正月やひな祭り、結婚式などのイベントで何度でも着用できます。
ご自宅で好きな時に記念写真を撮ることも可能です。
3. 兄弟姉妹で着回しができる:
下のお子さまがいる場合、お下がりとして着用させることができます。
長期的に見れば、レンタルを繰り返すよりも費用を抑えられる可能性があります。
4. 記念として残せる:
お子さまの成長の証として、形に残すことができます。
将来的には成人式の前撮りや、お孫さんの七五三で活用するなど、代々受け継いでいくことも夢ではありません。
購入のデメリット
1. 初期費用が高い:
レンタルに比べて、一度にかかる費用は高くなります。
着物本体だけでなく、帯や小物類も揃えるとなると、さらに費用がかさむことがあります。
2. 保管場所と手入れが必要:
着物は湿気に弱く、虫食いのリスクもあるため、適切な保管場所と定期的な虫干しなどのお手入れが必要です。
着用後のクリーニングも欠かせません。
3. 子どもの成長に合わせてサイズ直しが必要:
「身上げ」や「肩上げ」で調整できるとはいえ、子どもの成長は早いです。
数年後に再度着用する際は、サイズ直しが必要になることがほとんどです。
4. トレンドの変化:
着物の流行は緩やかですが、全くないわけではありません。
数年後に着回す際に、デザインが少し古く感じる可能性もあります。
レントや購入、それぞれの特徴を踏まえ、ご家庭にとって最適な選択をするためのポイントをご紹介します。
★費用面:予算と着用回数で考える
七五三にかかる総費用(着物、着付け、ヘアメイク、写真撮影、会食など)の予算を決めましょう。
レンタルは初期費用が安く済みますが、兄弟姉妹で何度も着る予定があるなら、長い目で見ると購入がお得になる場合もあります。
★手間:保管や手入れの負担をどう考えるか
着物の保管場所の確保や、着用後のクリーニング・手入れに手間をかけたくないなら、断然レンタルがおすすめです。
記念として残したい、次も使いたい場合は購入を検討しましょう。
★兄弟姉妹の有無:着回しの可能性
下のお子さまがいて、将来的に着回しを考えている場合は、購入がおすすめです。
性別や年齢差も考慮してください。
★こだわり:デザインやサイズへの思い入れ
「このデザインや色がいい」「ぴったりのサイズが希望」など強いこだわりがあれば購入がおすすめです。
レンタルだと希望通りのものが選べない場合もあります。
スタジオ101では、お出かけ用の着物では借りることが出来ないような、アンティーク着物を着ることが出来ます。
お参りに着物で行くのは、お子様にとってはかなりご負担も大きくなります。
でも、七五三写真は着物で撮影をしたい・・・そんな皆様は、是非当店の撮影をご利用ください。
レンタルも購入も、それぞれに良さがあります。
どちらかが絶対正解というわけではありません。
ご予算やお祝いのスタイル、ご家庭の考えに合わせて、最適な方法を選びましょう。
何より大切なのは、お子様と家族みんなが笑顔で過ごせることです。
じっくり検討して、最高の七五三をお迎えくださいね!
七五三のお祝いで子どもたちが着る着物には、いくつか特別な種類があります。その中でも「一つ身(ひとつみ)」や「五つ身(いつつみ)」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。これらは、子ども用の着物のサイズや種類の名前です。わかりやすく説明しますね。
「三つ身」は、3歳の女の子や男の子が着るための小さな着物です。ちょうど幼児期の子ども用で、軽くて動きやすいのが特徴です。親や祖父母が子どもに合わせて買ったり、レンタルしたりします。とてもかわいくて、初めての七五三にぴったりの格好です。
「五つ身」は、七五三のお祝いで女の子が着る、「振袖(ふりそで)」と呼ばれる長い着物の種類です。5~7歳の女の子が正式に着る着物で、もっと華やかで飾りも多いです。大人の着物に近いデザインなので、とてもきれいです。着物の長さや柄も豪華です。
七五三のお祝い、お子様が着る着物選びも楽しみの一つですよね。でも、「一つ身」とか「三つ身」とか「四つ身」といった聞き慣れない言葉が出てきて、戸惑ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
難しく考える必要はありません! 七五三の着物で出てくる「〇つ身(み)」という言葉は、簡単に言えば「どのくらいの年齢の子どもが着る着物か」という、着物のサイズの目安を表す言葉なんです。昔ながらの着物の生地の取り方から来た呼び方ですが、今は「赤ちゃん用」「3歳用」「7歳用」という感覚で大丈夫ですよ。
それでは、それぞれの「〇つ身」がどんな着物なのか、順を追って見ていきましょう。
大人の着物は体格に合わせてぴったり作りますが、子どもは成長が早いですし、少し大きめの着物を買って、長く着せたいということもありますよね。そこで登場するのが「身上げ(みあげ)」と「肩上げ(かたあげ)」という、子どもならではの着物の工夫です。
身上げ:着物の丈が長い時に、腰の部分で布を内側に折り込んで縫い、子どもの身長に合わせて丈を調整すること。
肩上げ:袖が長い時に、肩の部分で布を内側に折り込んで縫い、袖の長さを調整すること。
これらの「上げ」の部分は、着物を成長に合わせて調整できるようにするための「しるし」でもあり、また、子どもの可愛らしさを引き立てるデザインの一部でもあります。七五三の着物を選ぶ際は、この「上げ」がされているかどうかもチェックポイントになります。
それでは、いよいよ本題の「〇つ身」についてです。
対象年齢の目安: 主に0歳~1歳頃の赤ちゃんや乳幼児が着る着物です。七五三では、3歳のお子様でも小柄な場合や、兄弟のお宮参り用として使われることもあります。
特徴: 大人用の着物を作る反物(生地)1枚から、縫い合わせなしでそのまま裁断して作れる、一番小さいサイズの着物です。まだおむつをはいている赤ちゃんにも着せやすいように、比較的シンプルに作られています。
用途: お宮参りや初節句などでよく見られます。七五三の3歳で着る場合は、この着物に袖を通すことで、より幼く可愛らしい印象になります。

対象年齢の目安: 主に2歳~3歳頃の子どもが着る着物です。まさに七五三の3歳のお祝いで最もよく使われるサイズです。
特徴: 大人用の反物1枚から、子ども用の着物を2枚と、大人用のはんてん1枚(または子ども用着物3枚)が取れるくらいの生地を使って作られる、という意味合いから「三つ身」と呼ばれています。実際に反物の取り方を気にすることはほとんどありませんが、この着物も「身上げ」と「肩上げ」で子どもの身長や腕の長さに合わせて調整できるのが特徴です。
用途: 七五三の3歳のお祝いがメインです。華やかな柄が多く、可愛い帯や被布(ひふ)を合わせてお祝いします。

対象年齢の目安: 主に5歳~7歳頃の子どもが着る着物です。七五三の5歳(男の子)と7歳(女の子)のお祝いで最もよく使われるサイズです。
特徴: 大人用の反物1枚から、子ども用の着物が3枚と大人用のはんてん1枚(または子ども用着物4枚)が取れるくらいの生地を使って作られる、という意味合いから「四つ身」と呼ばれています。三つ身よりも少し大きめの作りで、「身上げ」と「肩上げ」で調整できる点は同じです。この年齢になると、袖の長さや身幅など、大人用の着物に近い仕立てになります。
用途: 七五三の5歳男の子の羽織袴や、7歳女の子の振袖タイプの着物によく使われます。この年齢になると、大人に近い着付けをすることで、より凛々しく、または優雅な姿を演出できます。
昔の着物生地の取り方から来た言葉で、今はあまり深く考える必要はありません。
「この着物はだいたい何歳くらいの子が着るものか」という、着物のサイズの目安だと思ってください。
子どもの着物には「身上げ」や「肩上げ」という、成長に合わせて丈や袖を調整する特別な工夫がされています。
レンタルを利用する場合、通常はお子様の身長に合わせてすでに「上げ」が調整されていることが多いので、あまり意識する必要はないでしょう。
お子様の年齢や体格に合わせて、ぴったりで可愛い(かっこいい)着物を選んで、素敵な七五三をお祝いしてくださいね!

七五三はお子さまの成長を祝う大切な節目であり、主役はもちろん子どもですが、家族全員の装いも雰囲気を大きく左右します。
特に7歳の七五三は着物や帯を本格的に着付ける節目のため、家族の服装もそれに合わせて整えることが望まれます。
母親は和装であれば訪問着や色無地が定番で、控えめながらも品のある柄を選ぶと良いでしょう。
訪問着は季節や会場に合わせて選べば華やかさがありつつ、子どもの衣装を引き立てる役割を果たします。
色無地も帯の合わせ方次第で上品に仕上がり、特に落ち着いたトーンの色味は神社での参拝にも相応しい雰囲気を醸し出します。
洋装の場合は、シンプルで上質なワンピースやフォーマルスーツが一般的で、派手すぎる柄や露出の多い服は避けるべきです。
お祝い事にふさわしい柔らかな色合いや落ち着いたトーンを意識すれば、写真全体のバランスが良くなります。
父親の服装はスーツが基本です。濃紺やチャコールグレーなど落ち着いた色味が好まれ、ネクタイやポケットチーフでさりげない華やかさを加えると、お祝いらしさが演出できます。
黒一色の礼服は弔事を連想させてしまうため避けた方が良いとされます。
ビジネススーツを着用する場合も、靴やベルトをしっかり整え、清潔感を意識することが大切です。
父親は撮影の際に子どもを抱きかかえたり、歩きやすいようにサポートする場面も多いため、フォーマルでありながら動きやすい服装が望ましいでしょう。
兄弟姉妹の服装も意外に見落としがちなポイントです。主役が目立つように、派手すぎない清潔感のある服を選ぶのが基本です。
女の子であればシンプルなワンピースやブラウスにスカートを合わせ、男の子はシャツにベストやジャケットを合わせると、写真全体に統一感が生まれます。
小さな子どもの場合、着物を着せるケースもありますが、主役の7歳を引き立てる配慮を忘れないようにすると、全員の写真がまとまりやすくなります。また、移動や長時間の参拝で疲れてしまう可能性もあるため、着替えや防寒用の羽織を用意しておくと安心です。
祖父母が参加する場合も服装選びには注意が必要です。
祖母は留袖や訪問着といった和装も適していますが、洋装ならシックで落ち着いた色味のフォーマルウェアを選ぶと良いでしょう。
祖父はスーツやジャケットスタイルが一般的で、清潔感を意識することが大切です。親族全員で揃った写真を撮ることも多いため、事前に「和装で揃えるのか」「洋装で揃えるのか」といった方向性を家族間で確認しておくと統一感が生まれます。
ここまで大分固い内容で書いてしまいましたが、一番大事なのは家族全員が笑顔で居られることです。
七五三はケースバイケース。
その為に一番適している服装で行けると良いでしょう。
七五三はお子さまの健やかな成長を祝う、日本ならではの伝統行事です。特に7歳の女の子は「帯解きの儀」に由来し、それまで付け紐で着物を着ていたのが、本格的に帯を結ぶ年齢にあたります。つまり、子どもから一歩大人に近づく大切な節目なのです。現代では儀式自体は行われませんが、華やかな帯を結んだ四つ身の着物を着ることで、その歴史と文化を体験できます。七五三の着物には「大人になる準備ができた」という意味が込められているのだと知ると、より一層特別な気持ちでお祝いの日を迎えられるでしょう。
7歳の七五三で多く選ばれるのが「四つ身」と呼ばれる着物です。これは大人の振袖を小さく仕立てたようなもので、袖丈が長く、見た目もとても華やかです。四つ身は成長を見越して大きめに仕立て、肩や腰の部分を縫い上げてサイズを調整します。成長に合わせて縫いを下ろすことで長く着られるよう工夫されており、昔から子どもの健やかな成長を願う知恵が込められてきました。ご家庭によっては姉妹や親戚で受け継がれることもあり、代々着用される着物には家族の思い出がたっぷり詰まっています。こうした背景を知っていると、ただの衣装以上に「伝統を受け継ぐ特別な一着」として感じられるはずです。
7歳で帯を結ぶことは、七五三の大きな見どころです。帯には袋帯や名古屋帯などがありますが、子ども用には簡単に着付けられる「作り帯」が人気です。作り帯は完成した形を背中に取り付けるだけなので、時間がかからず着崩れもしにくいのがメリットです。結び方は「蝶結び」や「ふくら雀」が定番で、どちらも子どもの可愛らしさを引き立ててくれます。帯は着物と同系色にすると上品に、反対色を選ぶと華やかに映えるので、全体のバランスを考えて選ぶと良いでしょう。後ろ姿は写真にも残る大切なポイントですので、プロの着付け師に依頼するとより安心です。
着物姿をさらに華やかにしてくれるのが小物や髪飾りです。「はこせこ」や「末広(扇子)」、「しごき帯」など、七五三ならではの小物にはそれぞれ意味があります。たとえば、末広は「末永く幸せに」という願いを込めた縁起物です。髪飾りも大切で、赤やピンクのお花や簪を付けると一気に華やかさが増します。最近は洋風のヘアアクセサリーを取り入れるお子さまも多く、可愛らしい雰囲気や大人っぽさを演出することもできます。小物一つひとつが持つ意味を知ったうえで選ぶと、お子さまだけでなくご家族にとっても思い出深い体験になるでしょう。

筥迫(はこせこ) は、昔の女性が懐に入れていた小物入れのこと。 江戸時代の武家女性や裕福な町娘たちが、懐紙(かいし=手紙や化粧直しに使う紙)や香袋、小さな鏡などを入れて持ち歩いた、いわば「和装のポーチ」です。七五三では、3歳や7歳の女の子が着物を着るときの 帯まわりの装飾品 として用いられます。実際に物を入れるわけではなく、飾りの意味が大きいです。
帯の前に差し込むことで、着物姿に 華やかさと格式 を添えます。箱迫・扇子・びらかんざしなどは「しごき」「草履バッグ」と並んで、女の子の七五三を彩る小物セットの一部です。七五三では「お守り」「女の子としてのたしなみ」の象徴として身につける意味合いがあります。
七五三の着物は色や柄にも意味があります。赤は昔から魔除けの色とされ、健康や長寿を願う意味があります。紫は高貴さを表し、ピンクは可愛らしさを象徴します。柄では鶴や亀、松竹梅などおめでたい文様が多く用いられます。蝶や桜などは華やかさを表し、御所車や花丸文様は格調の高さを示します。最近は水色や黄色などモダンな色合いも人気で、写真映えするスタイルとして選ばれることも増えています。ただ、古典柄には「お子さまが幸せに育ちますように」という願いが込められているので、その意味を知ると選ぶ楽しさも広がります。
着物に合わせる草履は、サイズが合っていないと歩きにくく疲れてしまいます。7歳用の草履は台の高さも低めで、色柄も着物とコーディネートされています。移動が多い場合には、歩きやすい靴を持参して写真撮影の時だけ草履に履き替えるのもおすすめです。足袋は清潔感のある白が基本で、最近は滑り止め付きの足袋も販売されています。普段履き慣れないものだからこそ、事前に何度か履かせて慣れておくと当日も安心です。足元は意外に写真にも残りますので、全体の雰囲気に合わせて準備してあげましょう。
着物をレンタルにするか購入するかは、多くのご家庭が悩むところです。レンタルは種類が豊富で管理の手間がなく、費用も比較的抑えられます。一方で購入すれば記念として残せますし、姉妹や親戚に引き継ぐこともできます。価格はレンタルで数万円、購入でフルセットなら10万円前後かかることもありますが、「思い出を残すか」「手軽さを優先するか」で選ぶと納得しやすいです。写真館によっては撮影とセットになったレンタルプランもあるので、事前に比較して決めると良いでしょう。どちらを選んでも、お子さまが嬉しそうに着物を着ている姿が一番の宝物になるはずです。
着物は着付けに時間がかかるため、当日は余裕を持ったスケジュールが大切です。子どもの体型は大人に比べて凹凸が少ないため、補正タオルを使って着崩れを防ぎます。着付けの間に退屈してしまうお子さまもいるので、短時間で仕上げられるようプロにお願いするのがおすすめです。また、写真撮影や参拝で長時間歩くことを考えて、こまめに休憩を取ることも大切です。おやつや飲み物を用意しておくと気分転換になります。着崩れが起きたときのために安全ピンや腰ひもを持参すると安心です。準備を丁寧に行えば、お子さまもご家族も笑顔で一日を過ごせるでしょう。
最近は着物に洋風のアレンジを取り入れる方も増えています。たとえば着物にブーツを合わせたり、髪型を洋風にアレンジしたりすることで、伝統と現代が融合したスタイルを楽しめます。写真館によってはドレスと着物の両方を着られるプランもあり、子どもの「可愛い」を存分に楽しめます。ただし神社での正式なご祈祷には伝統的な着物が望ましいため、場面によって着分けるのがおすすめです。七五三は形式にとらわれすぎず、お子さまが心から楽しめる形で祝うことが一番大切です。
7歳の七五三で着る着物は、お子さまの成長を祝い、ご家族の愛情を形にする特別なものです。四つ身の着物や帯、小物にはすべて意味があり、古くから受け継がれてきた伝統が詰まっています。現代ではレンタルや洋風アレンジなど選択肢も広がり、自由なスタイルで楽しむことができますが、どのような形であれ「お子さまの健やかな成長を願う気持ち」が一番の中心です。七五三の日に撮った写真は、数十年後に見返してもご家族の笑顔と愛情を思い出させてくれる宝物になります。着物の意味や豆知識を知って準備を進めれば、きっと忘れられない一日になるでしょう。
千葉県千葉市花見川区花園1-9-3 101にある子供写真スタジオSTUTIO LEMON 101!
オシャレに美しい七五三写真を撮影できます!
JR総武線 新検見川駅徒歩1分
七五三撮影はこちらから!
七五三前撮り・後撮りもやっています!

